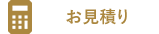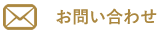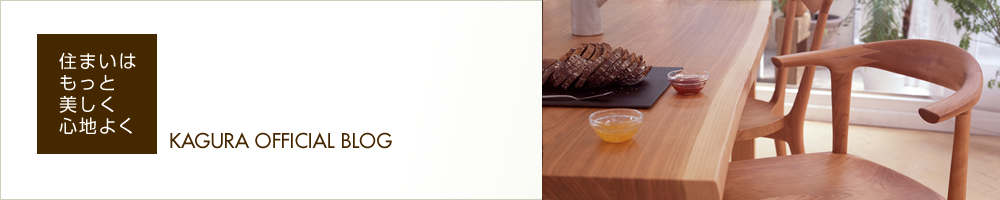
現代に息づく伝統技術 無垢材家具を木組みでつくるということ
2022.3.11

私たちの生活にはいわゆる家具というものは欠かせません。
安価なものから比較的高価なもの、製法や素材も様々ですが、その寿命=ライフサイクルはどの程度に考えて家具選びをしているでしょうか。
数年?数十年?孫の代まで?
意外とここについては数年程度のサイクルでの買い替えを考えている方も多く、それ自体は間違ったことではありません。
しかし我々家具蔵は長く使える「一生もの」を念頭に原木の買い付けからこだわって無垢材を使用し、伝統的な工法で一つ一つ木組みで無垢材家具を作っています。
大きな工場でのいわゆるライン生産・大量生産とは異なり、創業以来、熟練の職人が木取りから完成までを手仕事で行っています。
これには当然、技術や知識が必要となり、特に木組みには、高度な加工技術が必要不可欠です。
木という素材の特性を理解し、用途に応じた工法を用います。
その工法は、昔から日本人が培ってきた伝統的なものです。
その木組みについて掘り下げてお話しをしていきましょう。
日本の住まいと家具蔵の無垢材家具の共通性は「木組み」にあり!

木組みとは、「木材同士の接合を釘や金物などに頼らず、木材そのものを互いにがっしりとはめ合わせていくことで力強い骨組みを作り上げていく」伝統工法のことを指します。
この接合には「継手」「仕口」と呼ばれる様々な手法があり、古来より日本の職人たちによって受け継がれ、洗練されてきました。
近年、木造建築の主流となっているのは「在来工法」と呼ばれる技術です。
これは戦後に住宅の大量・短工期・ローコスト生産が求められたことにより発展しました。
骨組みとなる木材にはあらかじめコンピューター制御によるプレカット加工を施しておき、それらの建材を金物類の力で引き寄せて骨格を組んでいく構法です。
プレカットでの加工は建築工期の短縮、コストの削減などの利点がある一方、機械ではどうしても対応できない接合部の加工があり、それを補うための金物の力が必要となるのです。
伝統工法と在来工法の大きな違いの一つは、作り手が木材に注ぐ熱量の差にあると言えるかもしれません。
プレカットの機械による均一な加工に対し、伝統工法では職人が一本一本の木の表情やクセを見極め、たとえ年月がたってもその木の本来持っている力が最大限に発揮されるような使い方を導きだし、一箇所ごとに細かな手刻みを施していきます。
大工さんは昔から「木は木で締める」と言ってきましたが、これも素材同士の相性を見抜いた知恵といえるでしょう。
家具蔵の家具作りも日本伝統の木組みの手法を家具作りに取り入れています。
「木は木で締める」製法は例えば無垢材チェアの強度を高める為、無垢材テーブルの板と板をより強固に接合するために使われ、より長く使用できる無垢材家具作りを行っています。
木組みは強度を出すことができる

昔の日本の住まいは木の梁と柱をがっちりと組む、伝統的な工法で家を建てていました。
木に墨付けをして刻み、組む順番を正しく考えながらしっかりと挿し合わせるという伝統工法は、40年ほど前までは日本のどこでも行われていました。
しかし現在では、寺社などを建てる宮大工を除き、伝統工法を行う町屋の大工さんは、ほとんどいなくなってしまっている現状です。
金物は、一度曲がってしまうと自然には元に戻りません。
それに対し木材は、切られない限りは自分で戻る力があり、木と木をしっかり挿し合わせておくと丈夫に長持ちします。
家具においても同じことがいえます。
例えば椅子において、現在は短時間の大量生産を目的とする為に脚と座面の部分を接合する際、ネジを使うケースが多くあります。
ただ、安易にネジなどの金物を使用すると長年の使用による破損につながり、だめになれば捨てるというサイクルの連鎖へと繋がってしまいます。
「木は木で締める」の言葉にもあるように、安易にネジなどの金物を使用しないことが、丈夫で長持ちする、世代を超えて使い込んでいくことができる丈夫な木の椅子、無垢材チェアに繋がるのです。
技術は伝統的、スタイルは現代的な無垢材家具を目指して

「伝統の技を大事にする」といっても、いたずらな懐古主義に走るということは、まったくありません。
日本人が昔から培ってきた伝統の技を用いながら、現代のライフスタイルに合ったすっきりとしたシンプルな空間から和洋様々な空間に馴染む無垢材家具をつくっていく。
ライフスタイルや好みが多様化した時代だからこそ、それに応じたさまざまな表現をかたちにしながら伝統的な技術を大事にしていく。
それこそが文化の継承であり、家具蔵の使命でもあります。
伝統的な技術は「古いものが残って来た」のではなく「時を越えてよいもの」であるからこそ、未来に繋げなければいけないのです。
木組みの無垢材家具は伝統が刻まれた職人の技があってこそつくることができます。
長い年月をかけ、日本のしっとりとした気候風土に合った家具は何よりも美しく、風景にもなじみ、飽きが来る事がありません。
そのうえで長持ちする高寿命のものは次の世代にも受け継いでいくことのできる、価値ある財産となるに違いありません。
この伝統技術を継承して、木組みの家具を多くの方にご提供することが私たちの使命であり、喜びです。

関連する記事
最近の投稿
- ラウンドテーブルの「脚」は何が正解か? 2025年4月3日
- 無垢材家具は樹種の堅さで選ぶべきか 2025年4月1日
- 一枚板テーブルは「乾燥」が重要である理由は? 2025年3月30日
- なぜ無垢材家具にはリピーターが多いのか? 2025年3月28日
- 無垢材は耳にも優しい!その理由とは? 2025年3月26日
- 大きなテーブルを選ぶときはここを確認! 2025年3月24日
- 「人が集まる」木をダイニングテーブルにする理由とは 2025年3月22日
- 「6人掛けテーブル」のサイズの正解は何センチか? 2025年3月20日
- 家具の周辺に必要なスペースの「目安」を知る 2025年3月18日
- 「座り心地が良い」という感覚は何から生まれるか 2025年3月16日
カテゴリー
- 未分類 (1)
- 家具の選び方・置き方 (1,570)
- インテリア&住宅情報 (634)
- 人と木と文化 (396)
- ニュース&インフォメーション (447)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (615)