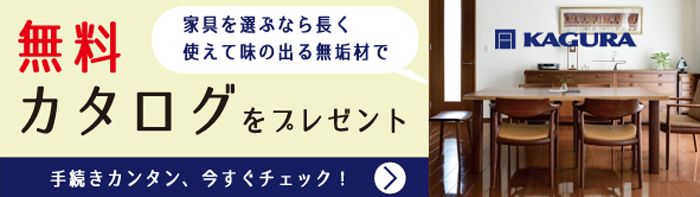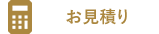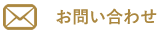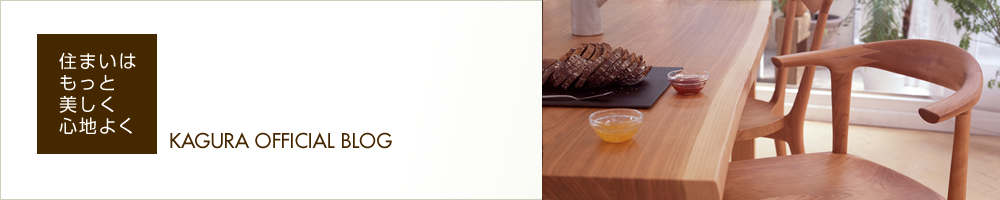
住まいづくりと家具選びは一緒に行うべき理由とは?
2024.4.29

住空間づくり、つまり家づくり・住まいづくりは毎日を心身ともに豊かにするうえで重要なプロセスとなり、慎重に行わなければなりません。
しかし家単体で、本当に心地良い暮らしは決して実現しません。
日々の生活に欠かせない「家具」もいわば空間の一部であり、これらの要素も合わせてはじめて「家」は「住まい」となります。
設計の段階から日常に使用する家具のことまで視野に入れて家づくりを進めることでそこに住まう人の生活スタイルに合った居心地の良い空間をつくることにつながります。
そこにいる人皆が居心地の良い住まいを実現するには間取りの段階でのインテリアプランも必要になってくるのです。
住まいづくりと家具選びの実情

一方で「住まいづくり」と「家具選び」は別々に考えられてしまうことが多々見られます。
それ自体が間違っているわけではありませんが、その理由は住まいの提案と家具の提案が別々になることが殆どであるからと言ってよいでしょう。
多くの場合、ハウスメーカーなどで「家」を相談し、その準備と設計・建築が進んでいきます。
そのあとに家具販売店で、予定されている、あるいは完成している住まいに合わせた「家具選び」が始まるということが一般的です。
家の新築はそれ自体が施主側も様々なことを決定するのでそれに頭が一杯になっているということも珍しくなく、これ自体はある意味で仕方のないことですが、少なくとも誤解を恐れずに言えば住む間際になって家具を見始めるのでは遅いと言えます。
このケースで起こりうることは間に合わせや妥協したインテリアプランになってしまう可能性があること、ひいては本当に快適な暮らし方を「我慢」することになりかねないことです。
せっかくの様々なこだわりを凝らした自慢の我が家です。
真の意味で快適性を持った空間にするためには間取り段階での家具選び、つまり住まいづくりと並行した家具の検討が必要です。
本当に快適な空間を作りあげるために

なぜ間取り段階で家具の検討が必要なのでしょうか。
その理由のひとつとして、置きたい家具や家電の大きさから部屋の広さや窓の位置など間取りも変わってくるという点が挙げられます。
インテリアプランはよく練っておかないと、日常において頻繁に使用する生活動線がうまく確保できないといったことも多々あります。
置きたい家具が事前に決まっていればその家具を中心とした間取りを考えることが可能になります。
必然的にレイアウトやそれに合わせた間取り設計にもなり、窓の位置や高さもそれに準じたものとなるでしょう。
リビングダイニングの中心となるダイニングテーブルやソファが事前に決まっていれば収納を作る場所もあるいは配置する場所も決まり、間取りそのものがスムーズに完成します。
例えば設計側の意見のままに窓を取り付けてしまったりすると、家具を決める際に消去法でサイズや置き方を決めることとなり、せっかくの新居での理想の暮らしから遠ざかってしまうのです。
あるいは家具のサイズや置き方が決まれば、照明位置や意外と見落としがちなコンセント類の数や位置も決めやすくなります。
「テーブルの中央に照明が来るのが理想なのにそうではない」
「住んでみたら延長コードだらけになり配線が見えて見栄えがしない」
「テレビを置く位置が不本意」
「家電を使用する際に使いにくい」
等のよく耳にする失敗を防ぐことができます。
カラーコーディネートもスムーズに

カラーコーディネートについても家具を含めた全体の見え方が空間の質を上下させます。
家具のカラーは部屋全体の雰囲気に大きな影響を与え、家具とコントラストを与えることが出来るフローリングやドアなどの建具を選ぶことで家具は引き立ちます。
逆に家具と同系色や調和する色を選ぶことで、統一感が生まれ同調させることで落ち着きのある空間づくりができるでしょう。
「住まいづくり」と「家具選び」を同時に行うことでカラーコーディネートもスムーズに行うことが可能となります。
収納計画に基づいて間取りを決めることができる

間取りについて考えることは同時に収納計画について検討することにつながります。
普段の暮らしの動線に対してベストな位置での収納の配置や取付けがあるはずです。
ここについても事前にダイニングテーブルなどの家具が決まっていることでどのような収納スタイルがベストかなどを決定しやすくなります。
あるいはここは間取り=収納計画が完成してから着手してもいい部分かもしれません。
住まいに備え付けられている収納から不足している部分を補完することができるのが置き型の収納家具であり、あるいはキッチンのバックセット(背面収納)などはハウスメーカーやデベロッパーの提案するものよりも家具販売店の提案するものの方がクオリティも高く割安になることも少なくないからです。
さらには空間における「バランスと対称性」を最良のものにでき、空間全体に整った印象を与えることができる点。
採光と風通しを考慮した設計が可能になる点など、これらも「住まいづくり」と「家具選び」を同時に行う大きなメリットです。
私ども家具蔵では住まいの計画段階のお客様へ対しても、住む人の理想的な家具、それを設置できる空間づくりを包括的に提案し、家具の配置・素材選びを含めた空間づくりのアドバイスを行っています。
「住まいづくり」の計画段階で「家具選び」についても相談することで、より質の高い空間へと近づくはずです。
新築、引越、リフォームの機会の際は「家具から始める家づくり」を標榜する私ども家具蔵へお問合せ下さい。
 トータルインテリアコーディネート無料相談会(3D PLAN)のご相談はこちらから
トータルインテリアコーディネート無料相談会(3D PLAN)のご相談はこちらから
関連する記事
最近の投稿
- ラウンドテーブルの「脚」は何が正解か? 2025年4月3日
- 無垢材家具は樹種の堅さで選ぶべきか 2025年4月1日
- 一枚板テーブルは「乾燥」が重要である理由は? 2025年3月30日
- なぜ無垢材家具にはリピーターが多いのか? 2025年3月28日
- 無垢材は耳にも優しい!その理由とは? 2025年3月26日
- 大きなテーブルを選ぶときはここを確認! 2025年3月24日
- 「人が集まる」木をダイニングテーブルにする理由とは 2025年3月22日
- 「6人掛けテーブル」のサイズの正解は何センチか? 2025年3月20日
- 家具の周辺に必要なスペースの「目安」を知る 2025年3月18日
- 「座り心地が良い」という感覚は何から生まれるか 2025年3月16日
カテゴリー
- 未分類 (1)
- 家具の選び方・置き方 (1,570)
- インテリア&住宅情報 (634)
- 人と木と文化 (396)
- ニュース&インフォメーション (447)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (615)