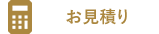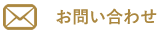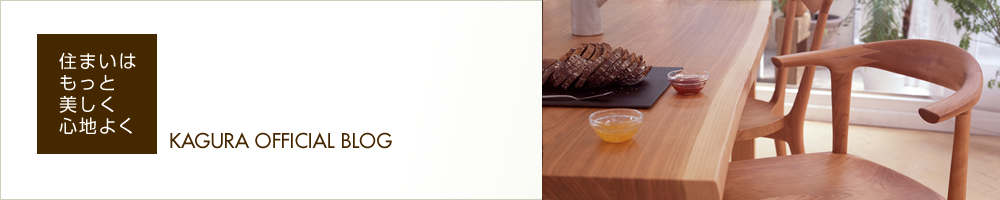
日本のキッチンの歴史
2019.11.16
キッチンという言葉は、日本語に訳すと「台所」です。
元々の語源から見ていくと、平安時代の頃にあったという「台盤所」が元になっているといわれています。
台盤所というのは、位の高い貴族たちが食事をするための部屋の総称であり、今でいうお皿を乗せる台がその部屋に置いてあったのでこの名前がつきました。
ちなみに、調理などを行う場所を台所と呼ぶことが世間的に浸透したのは中世以降になってからです。
そして、江戸時代以降になると、竹の簀の子などを使用するといった台所での仕事がなされるようになります。

明治時代になると文明開化が日本にやってきますが、台所に関しては大きな変化はありませんでした。
当時の台所は主に「床上空間」と「土間空間」の2種類に分けられており、床の上にはかまどがあり、土間には「つくばい」があるというのが普通でした。
燃料としてガスが使われるということも一般的ではなく、床上では専ら「かまど」と「七輪」が使われていました。
やがて水道が使われ始めると、土間の簀の子の上にある置き流し部分に水が注げるようになりましたが、しゃがまなければ火も水も使うことができず、かなりの苦労を強いられました。
しかし、この歴史の流れは「大正デモクラシー」の影響で大きく変わり始めます。
台所改善運動が起こるのです。
最も大きかったのは、しゃがまなければ使用できない台所を、どうすれば立ちながらでも使用できるのかという改良が進められたことです。
実際にこの改良が成果として現れるのは昭和時代になるまで待たなければいけませんが、これを期にガスや電気、水道の設備が見直されたのはとても大きなことでした。
さて、戦後になると、農村のほうではそれまでのかまどを使った火おこしや、井戸からの水くみといったハードな労働から徐々に開放されていく動きが起こりはじめました。
立つとしゃがむ、といったことを繰り返す作業をなくし、どうすれば立ったまま調理ができるようになるのかという生活改善運動が盛んになります。
ここには、火の使用の際にかまどから出る煤や煙といった、有害なものをなくすという提案も含まれていました。
一方で、同じ戦後でも、都市住宅のほうでは全く状況が異なり戦争の影響を大きく受けています。
戦前の時点で「ガスコンロ」や「ガスかまど」があるなど、農村部に比べて大きく発展していましたが、戦争が始まってからは環境が一変します。
台所の本来の役割は失われ、人々は飢えをしのぎ戦争をやり過ごすことだけに集中するようになっていました。
戦争によって電気やガスなども打撃を受け、外で炊事をすることを強いられる人も多かったといわれています。
昭和31年になると、いよいよ「ステンレス流し台」が登場し、あっという間に一般家庭に広まっていきます。
それまでは人造石や木製亜鉛鉄板張りが一般的だったと考えるとまさに画期的な発明でした。
同時に、現在では当たりまえの、「ダイニングキッチン」というスタイルも普及していきます。
ダイニングキッチンで何が変わったかというと、分けられていたお茶の間と台所が融合し、ちゃぶ台が西洋風のテーブルに変わりました。
さらに、ステンレス流し台が広まるに連れて、「炊飯器」や「冷蔵庫」といった便利な家電製品も普及し、台所仕事の大幅な効率化が進んだのです。
ステンレス流し台がこれほど普及した背景には、プレス工法というやり方で大量に作ることが可能になり、庶民でも買えるくらい値段が安くなったという理由があります。
昭和40年代の後半になると、ステンレス流し台よりも更に利便性の向上した「システムキッチン」が海外からやってきます。
当時の日本は高度経済成長期で、さまざまなものが海外から日本にやってきた時代でした。
その中の1つがシステムキッチンだったのです。
システムキッチンは用途に応じて収納ができる点やユニットなどを並び替えることができる点、多種多様なデザインを持っていて選べる点などが人々に受け入れられ、人気を博すようになります。
そして、海外からの輸入だったシステムキッチンも次第に、日本でオリジナルのものが作られるようになっていくのです。
また、進化しているのは台所だけではなく、冷蔵庫の冷凍室追加、食器の洗浄乾燥機、生ゴミの処理装置など、台所機器も次々と便利な製品が登場しています。
台所というのは、食事を取る必要のある人間にとってはなくてはならないものなので、台所が進化していくことは人間の幸せに直結していくことになるといえます。
現在では、台所には、利便性は高いのか、インテリアとしても機能するのか、居心地はいいのか、などが求められており、人々のニーズに合わせて台所は進化し続けています。
また、「ビルトインキッチン」という新たなスタイルも生まれており、これはガスコンロや食洗機などの寸法を測り、キッチンとビルトインしてしまうシステムのことです。
工事をする必要はありますが、さらに効率よく調理をすることが可能になりました。
そして今時代はそれぞれのニーズに応える「オーダーキッチン」も大きく浸透してきました。
画一的なシステムキッチンでは補うことのできない「痒いところに手が届く機能」や対面型のアイランドやペニンシュラといったスタイルが主流になってきたことからの「家具として見せるキッチン」の考え方の出現。
自然回帰の内装にも合う無垢材などを使用した木のキッチンも人気です。
家具蔵でも数多くの事例をもとに、「あなただけ」のオリジナルキッチンをご提案します。
これから新築やリフォームなどでキッチンをお考えの方はお気軽にご相談ください。
関連する記事
最近の投稿
- ラウンドテーブルの「脚」は何が正解か? 2025年4月3日
- 無垢材家具は樹種の堅さで選ぶべきか 2025年4月1日
- 一枚板テーブルは「乾燥」が重要である理由は? 2025年3月30日
- なぜ無垢材家具にはリピーターが多いのか? 2025年3月28日
- 無垢材は耳にも優しい!その理由とは? 2025年3月26日
- 大きなテーブルを選ぶときはここを確認! 2025年3月24日
- 「人が集まる」木をダイニングテーブルにする理由とは 2025年3月22日
- 「6人掛けテーブル」のサイズの正解は何センチか? 2025年3月20日
- 家具の周辺に必要なスペースの「目安」を知る 2025年3月18日
- 「座り心地が良い」という感覚は何から生まれるか 2025年3月16日
カテゴリー
- 未分類 (1)
- 家具の選び方・置き方 (1,570)
- インテリア&住宅情報 (634)
- 人と木と文化 (396)
- ニュース&インフォメーション (447)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (615)