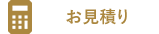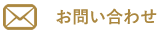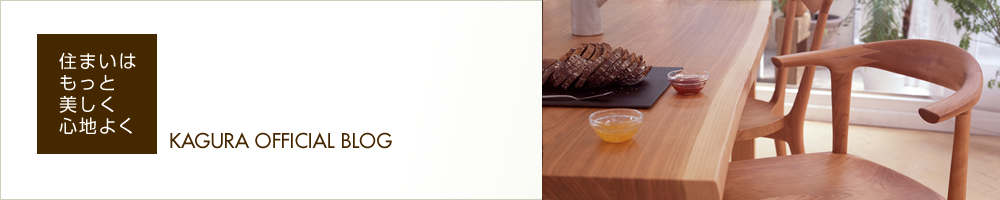
内装材の種類を知る
2018.1.22
家をつくるとき、リフォームやリノベーションなどの際に重要かつ皆さんが大きく悩まれるのが「壁材」です。
一般的に壁材と言っても種類も豊富にあり、それぞれの室内環境によってもこだわりが出てくるところでもあります。
今回は室内の主な壁材を中心に、それぞれの特徴をまとめてみました。
もし、壁材選びに迷われている方がいればご参考になれば嬉しく思います。
クロス類を知る
一般的な住宅の居室空間で最も多く使われているのが「壁紙」と呼ばれるクロス。
素材によって、ビニールクロスや紙クロス、織物クロスなどに分類され、それぞれ豊富な種類が揃っています。
●ビニールクロス
塩化ビニール樹脂などを主な素材とするビニールシートに紙などを裏打ちしたもの。
一般的に最も多く用いられている素材で、ハウスメーカーの商品住宅などでは、標準仕様となっているケースが多くみられます。
比較的安価なものから揃い、色やデザインのバリエーションも豊富、プリントを施したものだけでなく、凸凹のあるエンボス加工、発泡させたタイプなども揃っています。
施工がしやすいのも特徴で、耐久性や清掃性にも優れ、調湿性などを持たせたタイプなどもあります。
・紙クロス
パルプが原料の洋紙を原紙に、プリント加工やエンボス加工を施したもの。
欧米では多く用いられる素材で、輸入住宅などに取り入れているケースもありますね。
「こうぞ」や「みつまた」を原料とした和紙、月桃の茎から繊維を取り出しパルプにした月桃紙、一年草のケナフなど原料としたものなどもあります。
・織物(布)クロス
平織りや綾織、不織布などがあり、温かみのあるテクスチャーや重厚感が魅力ですが、価格は比較的高め。
ホコリを吸着しやすいので、お手入れははたきをかけるか掃除機を用いることが一般的。
塗壁類を知る
自然素材での家づくりが人気となっている中で徐々にシェアを伸ばしているのがこの「塗壁」。
伝統的な左官塗工法である塗壁の種類は、一般的に仕上げ(上塗り)に塗るものによって分けられます。
漆喰(しっくい)を塗ったものが「漆喰壁」、土で仕上げたものが「土壁」になります。
さまざまな素材や仕上げがありますが、いずれも、日本の気候・風土にも適応しており、調湿性・断熱性・防火性・防音性などに優れているのが特徴。
クロスと異なり仕上がりに継ぎ目が無いこと、刷毛、コテやローラーなどでさまざまな表情を生み出すことができるのもメリットです。
●漆喰(しっくい)壁
漆喰壁は、消石灰に砂と糊などを混ぜて土壁の上に塗るもので、滑らかな表面の日本独自の塗壁仕上げ。耐久性、調湿性、断熱性、防火性などに優れています。
色は白が基本ですが、色土や顔料を加えたタイプも。通常の塗装仕上げのように施工できるタイプ、漆喰を用いたクロスなど施工性を高めたものもみられます。
●プラスター
鉱物質の粉末と水を混ぜたもの。純白の仕上がりが特徴です。石膏を主成分にした石膏プラスター(乾燥に伴う収縮がほとんど無い為、壁面に亀裂が生じにくい)、作業性のよいドロマイトプラスター(糊材を必要としない為、混練りが容易で作業性が良い。強度は石膏プラスターの方が上)などがあります。
西洋漆喰とも呼ばれる仕上げです。
最も古い建築技法のひとつでエジプトのピラミッドやギリシャの建築などにも用いられました。
●土もの(土壁)
いわゆる土もの、もしくは土壁と呼ばれるものは、数奇屋建築や茶室などにみられます。
「京壁」とも言われ、上塗りの土によって、「聚楽壁」「大津壁」などの種類があります。
●珪藻土(けいそうど)
海や湖などに生息していた単細胞の植物プランクトンの死骸が堆積して出来た土層から採取されるもの。
多孔質である(多くの小さな穴を持つ)ことから、吸湿性、吸放質性、保温性、断熱性に優れる素材です。
地球環境に配慮したものとして人気の自然素材のひとつとなっており、仕上げパターンや色柄、施工性を高めたタイプなどさまざまな商品がみられます。
石膏ボードに直接塗り付けられるもの、クロスの上に塗ることができるリフォーム向けの商品、炭や繊維など他の素材を組み合わせたメーカー独自の商品もあります。
その他木質系などを知る
木質系の製品としての壁材は、天然木化粧合板(突板タイプ)や化粧シートタイプなどがあります。
天然木化粧合板は、合板やMDF(中質繊維板)などの基材に木材の薄い板を張り付けたもの。
化粧シートタイプは、樹脂やオレフィン、紙などのシートに、木目や石目、抽象的な柄などを印刷し、基材に張り合わせたものです。
木質系の壁材は、ひとつの面に用いて部屋のアクセントとしたり、腰壁として取り入れえるケースがみられます。
タイルは、耐久性や耐水性に優れるため、主に水まわりに用いられる素材ですが、最近では居室の床や壁材などでも、取り入れられるケースもみられます。
特に、調湿や消臭機能を持つタイル商品は、リビングやダイニング、ベッドルームなどで用いる例も増えてきました。
テクスチャーやデザインのバリエーションも豊富になり、さまざまなインテリアに合わせることも可能となります。
上記で挙げた仕上げ材以外にも、各メーカーから、さまざまな機能を持たせた素材がみられます。
●エッグウォール
卵の殻を粉砕し紙に吹き付けた仕上げ材。卵一個につき約1万個の気孔があり、その気孔が生活臭などの臭気の吸収や室内の余分な湿気の吸収などに効果のある壁材です。
●モイス
バーミュキライトという天然の粘土鉱物を主成分とし、この鉱物が持つ層間活性効果からVOC(揮発性有機化合物)の吸着・固定化・分解力を活用します。
モイスは珪酸カルシウム水和物(トバモライト結晶)の構造に、粘土鉱物・バーミキュライト(尾鉱)を均一かつ同一方向に分散形成し、これを機能のみならずテクスチャーとした内装仕上材です。
このトバモライトの比表面積に多さとバーミキュライトの結晶水の総合効果により、室内湿度の調和を促して湿度のコンデンサー的な役割をはたします。
その他にもたとえば、基材に特殊な加工を施したり珪藻土などを混ぜることで、調湿機能や消臭機能を持たせたものなどは、湿気の気になる納戸やクロゼット、洗面室などに用いられます。
また、キッチンや洗面室などに向いているのが、汚れがこびりつきにくく、汚れても落ちやすい加工が施されたパネル状の壁材(キッチンパネルなど)。
水や熱に強く、油汚れにも強いのも特徴で、目地も少ないのでお手入れが簡単なのもメリット。
タイル調のものや石目調のものなど色柄も豊富です。
家を建てる、あるいはリフォーム・リノベーションをされる際にはこうしたことは知らないよりも知っておいた方が断然満足のいく住まいづくりになることは間違いありません。
空間をつくるにあたって、大きく目に入る部分でもありますので、もし、内装材選びに迷っている方がいらっしゃったらお近くの家具蔵各店で声を掛けてみてください。
きっと、良いヒントがありますよ。
参考文献
彰国社刊 小原二朗・加藤力・安藤正雄編「インテリアの計画と設計・第二版」
彰国社刊 壁装材料協会発行「インテリア学辞典」
関連する記事
最近の投稿
- ラウンドテーブルの「脚」は何が正解か? 2025年4月3日
- 無垢材家具は樹種の堅さで選ぶべきか 2025年4月1日
- 一枚板テーブルは「乾燥」が重要である理由は? 2025年3月30日
- なぜ無垢材家具にはリピーターが多いのか? 2025年3月28日
- 無垢材は耳にも優しい!その理由とは? 2025年3月26日
- 大きなテーブルを選ぶときはここを確認! 2025年3月24日
- 「人が集まる」木をダイニングテーブルにする理由とは 2025年3月22日
- 「6人掛けテーブル」のサイズの正解は何センチか? 2025年3月20日
- 家具の周辺に必要なスペースの「目安」を知る 2025年3月18日
- 「座り心地が良い」という感覚は何から生まれるか 2025年3月16日
カテゴリー
- 未分類 (1)
- 家具の選び方・置き方 (1,570)
- インテリア&住宅情報 (634)
- 人と木と文化 (396)
- ニュース&インフォメーション (447)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (615)