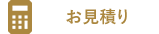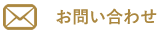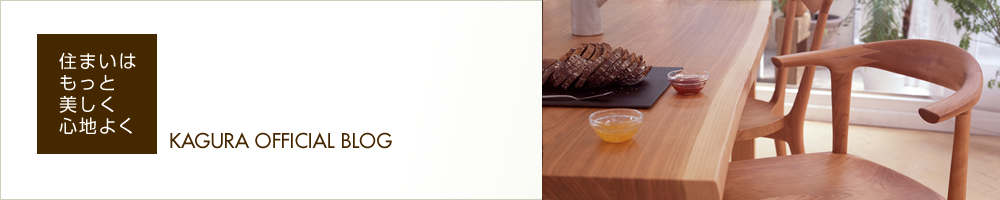
「住まいの香り -香りで心地よい暮らしを・第一回-」
2016.10.30
皆さん、こんにちは。
今年も富士山の冠雪のニュースが出ていました。
今年は過去最も遅い観測となった1956年に並ぶ遅さということでしたが、自然が少しずつ、季節の移り変わりを教えてくれますね。
季節はすっかり秋から冬に…と思っていたら、突然夏のような陽気が戻ってくるなど中々読めない昨今の気候ではありますが、今年もあと2か月余り。
しっかりと体調管理などに気を付けて過ごしたいものです。
さて、今回のブログは「香り」について。
お気に入りの我が家や、素敵な住まいを更にもうワンランクあげるのは「香り」かもしれません。
近年は「香りもインテリアの一部である」という考え方も浸透してきて、場所や気分によってやさしく香るアロマやお香を上手く使っているお住まいを拝見することもあります。
様々な方法で暮らしに香りを取り入れてみましょう、というのが今回のお話しです。
香りの効果で空間がグレードアップ
【香りの効果】
イライラしている時や気分が落ち込んだ時に、自分の好みの香りでリラックスできた。イライラが緩和されたという経験がある方はいるでしょうか?
これは、香りが脳の「大脳辺縁系」に作用しているから。
大脳辺縁系は、「好き・嫌い」「安全・危険」といった、感情や本能的な感覚をつかさどる部分のことで、人間の五感のうち嗅覚だけが直接この部分に伝わる仕組みになっています。
つまり、香りは人間の感情や心に直接的に作用し、時には気分をリフレッシュさせ、時には気持ちを落ち着かせ、あるいは集中力を高めてくれるような効果が期待できるというわけです。
さらに、香りの成分は呼吸によって肺に届き、肺静脈などから吸収されることで体にも作用します。
例えば、植物が出す香りには昆虫や動物を避ける・あるいは誘う効果や、殺菌・抗菌、仲間に危険を知らせる媒体としての役割があります。
皆さんが良く知っているバラの香りの主成分である「ゲラニオール」には強い殺菌力があるのですが、この香りをかぐことで、のどや気管が殺菌され、風邪の予防につながるということです。
ちなみに我々家具蔵が扱う無垢材も樹種ごとに特有の香りを作り出しています。
この香り成分の中でもっとも多いのが「テルペン質」と呼ばれる揮発性の成分。
かすかに漂うその香りは、ストレスや不安を和らげる心理的作用の他、気道の働きを良くする効果や血圧を下げる効果があったりします。
また、木の香りにはアレルギーのもとになるダニやカビを防ぐはたらきも。
清潔で快適な室内環境を維持する効果が無垢材の香りには含まれているのです。
その他、植物由来の香りには「細胞を老化させる活性酸素を抑える作用」「美白効果が期待できる香り」など女性必見の香りの種類もあるとのこと。
こうした香りの効果を生活に上手に取り入れていきたいものですね。
【香りの楽しみ方】
ここでは代表的な香りを楽しむためのツールをご紹介します。ご自分のライフスタイルに合う方法を取り入れてみましょう。
<アロマオイル>
植物の葉や花・果皮・樹皮・樹脂などから香りの成分を抽出して作られたオイルのこと。
アロマランプ(オイルを温め揮発させて香りを拡散させる)、アロマディフューザー(オイルを霧にして香りを拡散させる)が手軽にアロマオイルの香りが楽しめるアイテムとして人気です。
より簡単に香りを楽しみたい場合は、好みの容器にお湯を入れ、オイルを数滴たらすだけでもほのかな香りが楽しめます。
また、アロマオイルは家事にも活用できます。
ウェスや雑巾に少し含ませて拭き掃除に使う、水で薄めてアイロン時の霧吹きに使用するなど家事に香りを取り入れたい際にも便利です。
<アロマキャンドル>
ロウソクにアロマオイルを加えたもので、キャンドルに火をともすとやわらかい香りが広がります。
<お香>
お香の主な原料は、伽羅(きゃら)、沈香(じんこう)、白檀(びゃくだん)といった天然の植物で加熱すると芳香を発散するものです。
人類が生活の中に香りを取り入れた最初の形式といわれています。
最近ではアロマオイルが練り込まれたタイプもあり、香りはもちろん、形も豊富で使い方もさまざまです。
手軽に楽しめるのが、火を点火して使うタイプ。
お線香のようなスティック型は、燃える面積が均一なので香りも均一に広がっていきます。簡単に折れるので、燃焼時間の調節も簡単です。また、円錐型のものは下部に行くにしたがって煙が増えていくので、短時間で香りがお部屋に広がります
<芳香剤>
置いておくだけで気軽に香りが楽しめるのが芳香剤。
果実や樹木など、さまざまな香りがありますが、市販の芳香剤は形やサイズによって香りの広がり方が異なります。
置きたい場所に合った形やサイズを選ぶようにしましょう。
また、香りは空気よりも重くなるので、できるだけ部屋の高い所に置くのがお薦めです。
<ハーブ>
ラベンダー、ゼラニウム、ペパーミントなど香りの強いハーブ類は、香りが楽しめるうえに、グリーンインテリアとして楽しむことができます。
今回はここまで。次回は具体的な香りの効能やシーン別のお薦めの香りなどをご紹介します。
ご期待ください。
香りの効果で心地よいリラックス空間を…
関連する記事
最近の投稿
- ラウンドテーブルの「脚」は何が正解か? 2025年4月3日
- 無垢材家具は樹種の堅さで選ぶべきか 2025年4月1日
- 一枚板テーブルは「乾燥」が重要である理由は? 2025年3月30日
- なぜ無垢材家具にはリピーターが多いのか? 2025年3月28日
- 無垢材は耳にも優しい!その理由とは? 2025年3月26日
- 大きなテーブルを選ぶときはここを確認! 2025年3月24日
- 「人が集まる」木をダイニングテーブルにする理由とは 2025年3月22日
- 「6人掛けテーブル」のサイズの正解は何センチか? 2025年3月20日
- 家具の周辺に必要なスペースの「目安」を知る 2025年3月18日
- 「座り心地が良い」という感覚は何から生まれるか 2025年3月16日
カテゴリー
- 未分類 (1)
- 家具の選び方・置き方 (1,570)
- インテリア&住宅情報 (634)
- 人と木と文化 (396)
- ニュース&インフォメーション (447)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (615)