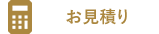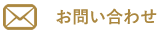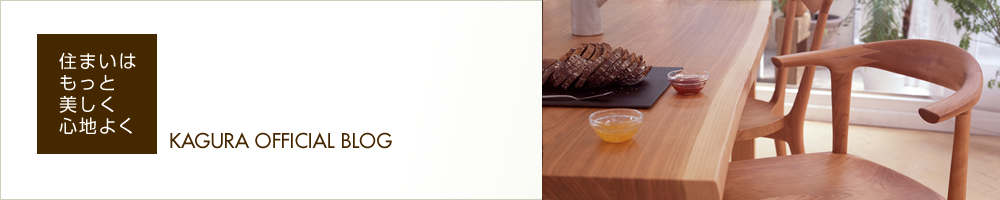
銀座と家具の歴史
2019.5.12
日本の家具の歴史は古く、奈良時代までさかのぼると言われています。
そもそも船大工がそのルーツであり、次第に宮大工へと変わった後に家具職人になっていったという説があります。
奈良時代から平安時代の家具や調度品を使っていたのは貴族です。
調度品の多くは漆塗りに蒔絵が施されていたり、または螺鈿で彩られたりといった作りのもので、優雅な暮らしに見合った、贅を尽くしたものであることが想像できるでしょう。
蒔絵や螺鈿は現代に至っても受け継がれている伝統工芸品の一つですが、奈良時代にはすでに今の中国から伝わっていたとされています。
当時は調度品だけでなく、建築装飾にも使われたと伝えられており、当時の贅沢な暮らしがうかがえます。
日本において家具や調度品を使う層は平安時代までは貴族が主でした。
江戸時代に入ると、武士など貴族以外の層にも家具や調度品は浸透していきます。
使われていたのは座椅子や脇息(きょうそく)、座卓などの他に文机、箪笥や長火鉢などで、貴族のような蒔絵や漆塗り、螺鈿のような贅沢なものではありません。
しかし、暮らしの中で欠かせないものとして重宝され、現代もそのまま使われている家具の原型の多くはこの頃に出来上がったと言っていいでしょう。
脇息(きょうそく)は、肘を置いて休息を取る際に使うもので、一般の生活の中で使われることはそうありませんが、座椅子や座卓、文机や火鉢などは、その後長い間日本で使われ続ける家具として残ることになるのです。
江戸時代以降、さまざまな発展を遂げた家具の一つに箪笥があげられます。
船中で使われていた船箪笥は、荒波での長旅にも耐えられるよう、頑丈な木に金具という作りで、商売に必要な印鑑や帳簿、筆や硯などが収められる引き出しが完備していました。
当時の箪笥は金庫として使われることも多く、商家では車箪笥という、下に車のついた箪笥も使われています。
これは、火事の際に箪笥を引くことで大切なお金を外に避難させやすくしたものです。
他にも、階段の役割を兼ねた階段箪笥や、薬屋や医者が使用した薬箪笥など、多くの箪笥が作られて活用されています。
明治時代から大正時代にかけて、婚礼の際に嫁入り道具として婚礼箪笥や鏡台などを持たせる習慣が広まり、家具はさらに庶民の暮らしに浸透することになります。
銀座で家具が商品として扱われるようになった正確な時期を把握するのは難しいですが、1930年代には銀座にデパートが立ち並ぶようになり、衣類や日用品などを中心に上質な商品が手に入るようになりました。
ファッションをはじめとした欧米文化が根付き始めた頃であり、家具も少しずつ欧米風のものが使われるようになった時代です。
とはいえ、テーブルやソファ、椅子など欧米風の家具が見られたのは上流の家庭が主であり、一般庶民の家庭ではまだまだ和家具が主流でした。
それでも、デパートやレストラン、カフェには欧米風のテーブルや椅子が置かれるようになり、庶民にとっても身近な家具として浸透していきました。
戦火で多くのものは焼けてしまいましたが、銀座では、現代もさまざまな老舗が残っています。
そして、家具店の中にもいくつかの老舗を見ることができます。
銀座といえば、上質な素材の商品が置かれているという印象を持つ人は多いでしょう。
家具も、銀座では質のよい素材を使ったものが多く扱われています。
ただし、上質な家具とは単に高価であるということではありません。
よい家具とは、職人やデザイナーがこだわりを持ち、丁寧に仕上げた家具であることを知っておきましょう。
高価なものは多いですが、それは素材だけにかかる金額ではなく、デザインをおこす時間や職人が作り上げていく時間の価格なのです。

木や革やファブリックといった、家具を作り出すために必要な素材選び、使う人の心地よさとインテリアとして目を楽しませるデザイン、部屋との調和などさまざまなバランスを考えて作り上げた家具こそが上質なものであり、銀座というこだわりを持った土地で手に入る商品と言えます。
銀座にはさまざまなブランド店も並んでいます。
銀座をブランドという視点だけで見ることなく、上質な家具が手に入る場所として捉え、自分に合った家具探しをすることが大切なのです。
もう一つ、よい家具を探すうえで忘れてはならないことがあります。
それは、長く愛用できるものであるということです。
長く使うためには、飽きがこないデザインであることも重要なポイントと言えるでしょう。
日本の四季に合った素材であるということも重要です。
そして、傷んだときにはリペアや調整ができることも考えておくと長く愛用できます。
例えば、革のソファであれば剥がれを修復したり色を変えたりすることも可能です。
木はワックスによって風合いが変わりますし、ファブリックも張り替えができます。
これらのアフターサービスを含めた条件を満たしているかどうかを、上質な家具選びのポイントにしてみましょう。
関連する記事
最近の投稿
- ラウンドテーブルの「脚」は何が正解か? 2025年4月3日
- 無垢材家具は樹種の堅さで選ぶべきか 2025年4月1日
- 一枚板テーブルは「乾燥」が重要である理由は? 2025年3月30日
- なぜ無垢材家具にはリピーターが多いのか? 2025年3月28日
- 無垢材は耳にも優しい!その理由とは? 2025年3月26日
- 大きなテーブルを選ぶときはここを確認! 2025年3月24日
- 「人が集まる」木をダイニングテーブルにする理由とは 2025年3月22日
- 「6人掛けテーブル」のサイズの正解は何センチか? 2025年3月20日
- 家具の周辺に必要なスペースの「目安」を知る 2025年3月18日
- 「座り心地が良い」という感覚は何から生まれるか 2025年3月16日
カテゴリー
- 未分類 (1)
- 家具の選び方・置き方 (1,570)
- インテリア&住宅情報 (634)
- 人と木と文化 (396)
- ニュース&インフォメーション (447)
- オーダーキッチン関連 (406)
- 一枚板関連 (635)
- オーダー収納関連 (615)